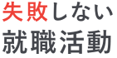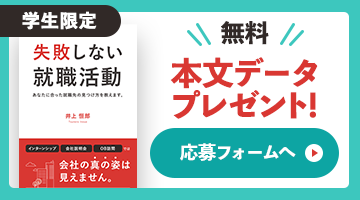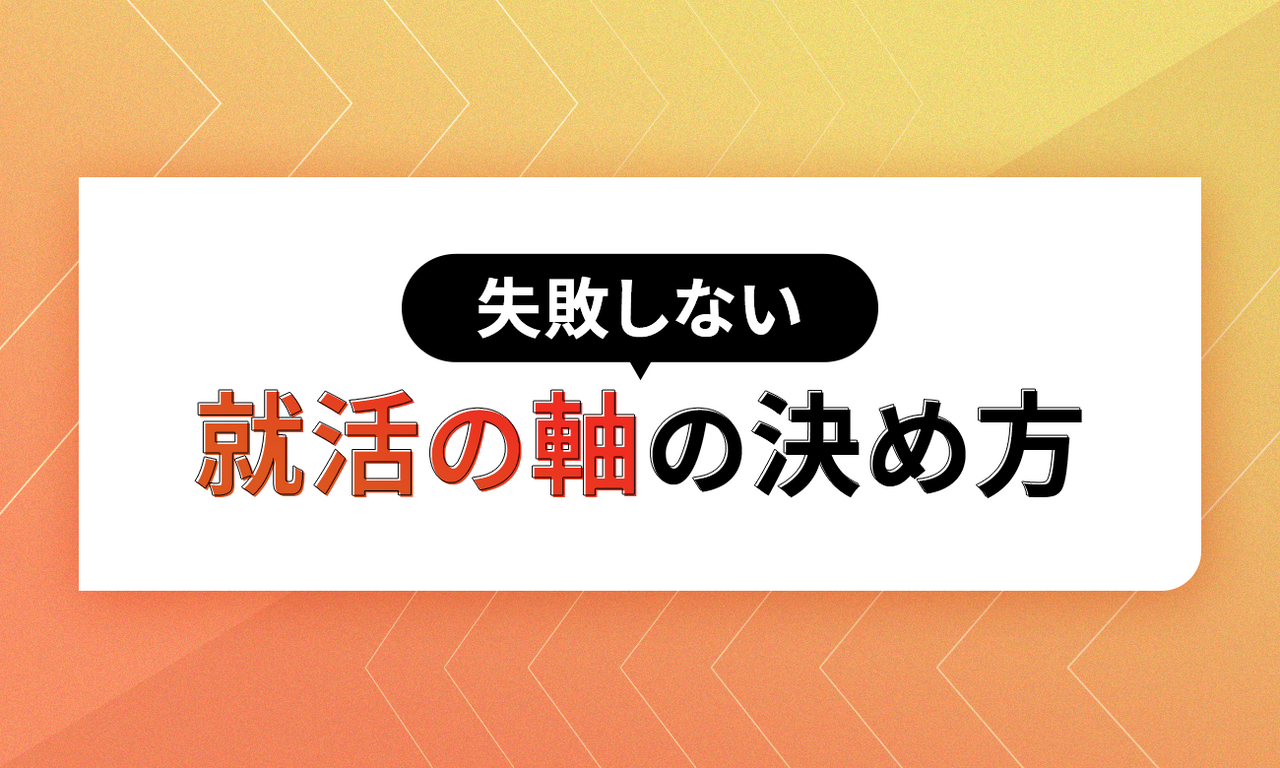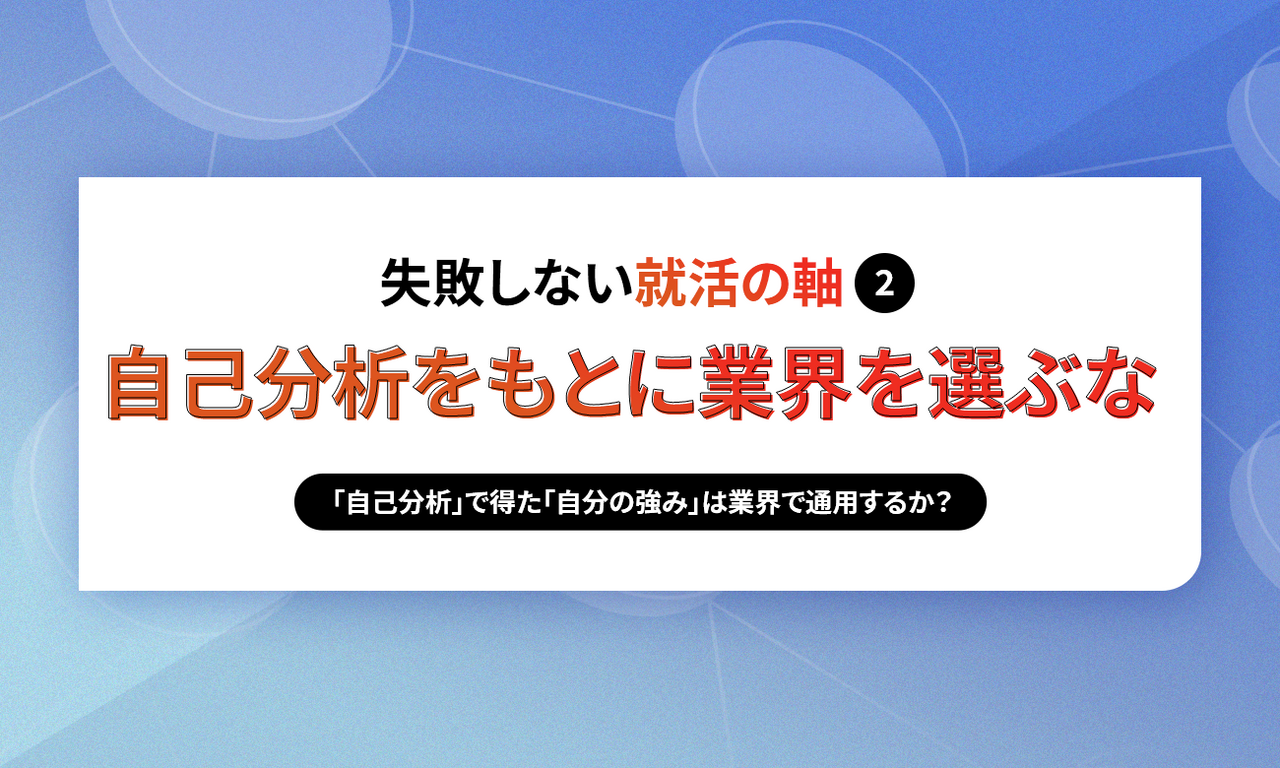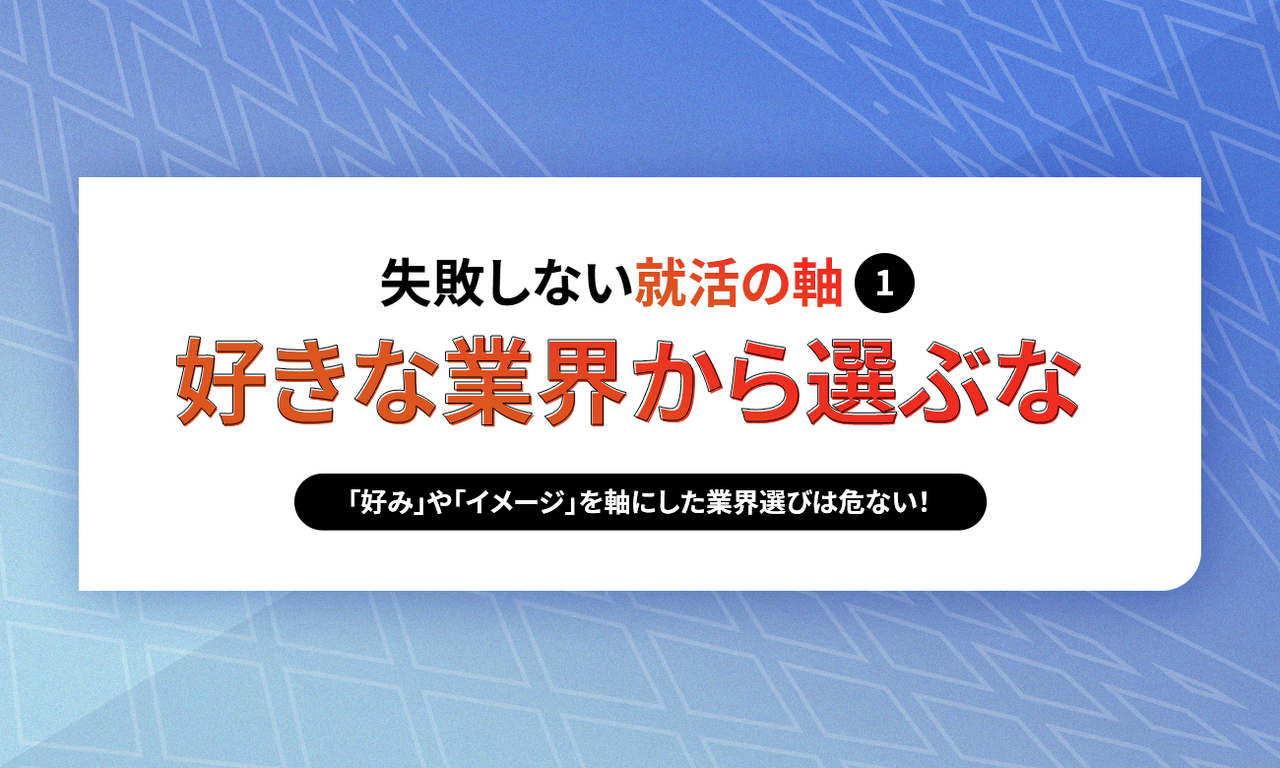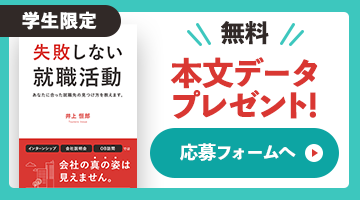【失敗しない就活の軸③】大学の専攻は就職に関係ない?ある?
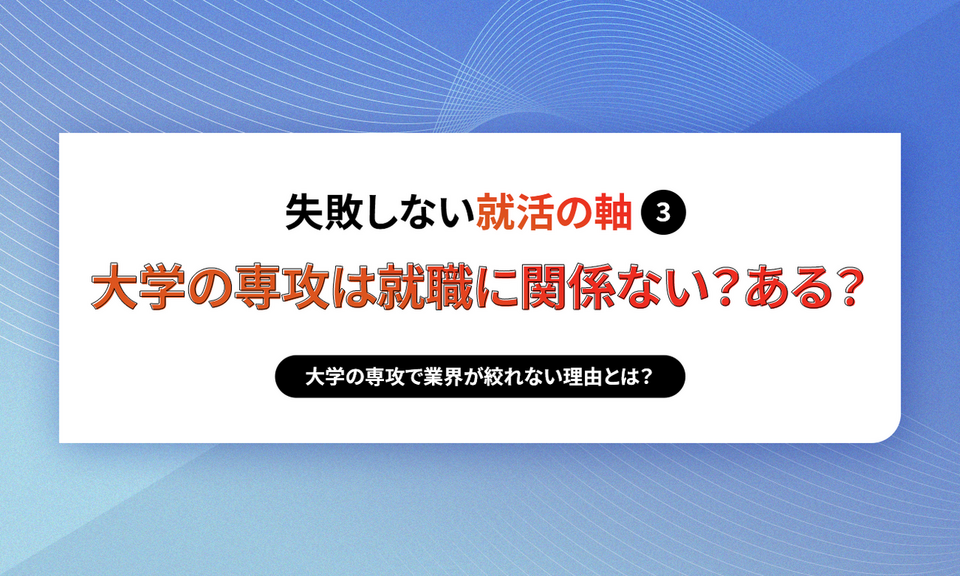
こんにちは!
「就活の軸」とは、業界や会社を絞る際の「自分なりの基準・条件」や「譲れない条件」のことです。
今回は就活で業界や会社の絞り方を考えるとき、「就活と大学の専攻は関係ない」3つの理由をご紹介します。
【関連情報】
【目次】
- 【理由①】企業は業務に大学の専攻を活かすことを期待していない
- <参考>就職に直結している学部・学科
- 【理由②】大学の講義内容がビジネスに直結していない
- <参考>学校教育に介入したエグゼクティブや企業
- 【理由③】学生生活に問題のある学生が多い
【就活と大学の専攻は関係ない理由①】企業は業務に大学の専攻を活かすことを期待していない
-
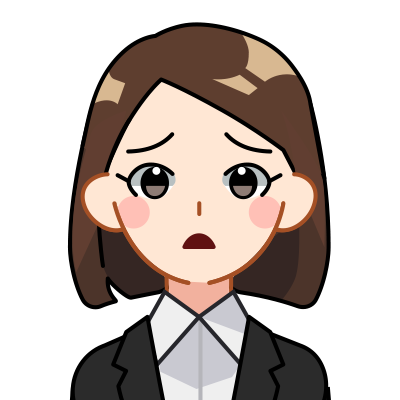
-
私の就活での業界の絞り方は「大学で頑張った専攻を活かせる会社」です。入社後は知識を活かして活躍したいと思っています。
-

-
残念ながら、多くの経営者は、学生に「大学の専攻を活かす」ことを期待していません。
あるテレビ番組で、日本電産の永守重信会長が新卒の大学生に対して苦言をていしていました。
「経営学部を出ても経営のことをまったく知らず、税金の仕組みすら分からない新卒の大学生が多い」
「(大学を出たにも関わらず)名刺の出し方も知らないという人が毎年大勢いる」
程度の違いこそあるにしても、多くの経営者たちが同じような思いを抱いているでしょう。
また日本経済団体連合会が1,376社に対しておこなった「2018年度新卒採用に関するアンケート調査」によると「企業が社員採用時に求める資質」で、「履修履歴・学業成績」は、全体のわずか4.4%でした。
-

-
このデータからもほとんどの企業が新卒者に対して「大学の専攻を業務に活かすことを期待していない」ことが明白です。
<参考>就職に直結している学部・学科
|
学部名 |
学科名 |
|
工学部 |
建築学・電気電子工学・機械工学・情報工学・土木工学 |
|
医学部 |
医学・看護学 |
|
薬学部 |
薬学 |
|
獣医学部 |
獣医学 |
|
歯学部 |
歯学 |
|
栄養学部 |
管理栄養学 |
-

-
ところが仮に専門性の高い分野を学んできたからといって、それらの知識を活かして、入社直後から第一線で活躍できると考えたら大間違いです。
とある設計事務所に入社した建築学科卒の例
大学の専攻を活かす意欲たっぷりで入社しましたが、社会人1年目に任される主な業務は次のような内容でした。
- 先輩が作成したラフをCADで図面におこす
- 役所に届けるための書類の作成
- 現場の写真撮影
- 打ち合わせの資料作成
- 打ち合わせの書記係 など
-
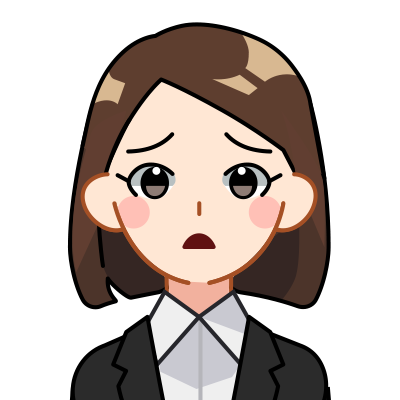
-
うえぇぇ。雑用や単純作業に追われる日々ですね。
-

-
その通りです。しかも残業も多く、土日出勤もあるでしょう
-
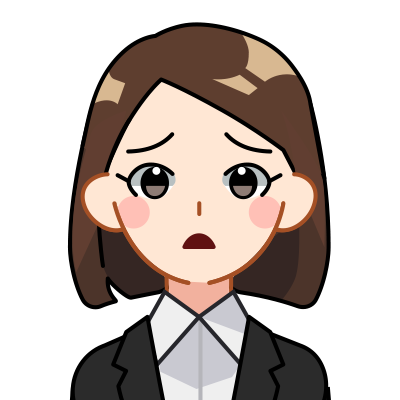
-
ひぃっ! き、きつそうだなぁ。全然イメージしていたのと違うんですけど……?
-

-
どの業界、どの仕事でも同じですが、最初の3年は「修行期間」だと思って辛抱しなくてはなりません。
しんどくて辞めたくなることもあるでしょうが、雑用を繰り返していくうちに、ビジネスに必要なスキルを体が勝手に覚えていきます。精神的にも余裕が生まれてくるでしょう。
そしてその頃になると、ようやく少しずつ雑用以外の仕事も任されるようになるのです。
【就活と大学の専攻は関係ない理由②】大学の講義内容がビジネスに直結していない
-
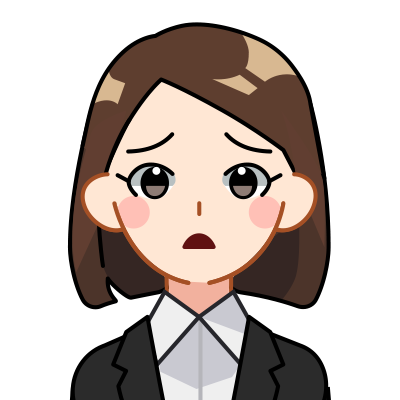
-
なぜ大学で専攻したことが仕事で活かせないのですか?
-

-
日本の大学は「専門的な学問を研究する機関」の意味合いが強く、講義がビジネス的な観点でおこなわれていません。つまりビジネス社会で必要な能力や知識を大学で身につけることは難しいと言わざるを得ないわけです。
坂本藤良氏(経営学者・評論家)の場合
東大経済学部を卒業した坂本氏は、慶応義塾大学の商学部の設立に参画した後、「経営学入門」などの経営学に関する様々な書籍を刊行し、「経営学の神様」と呼ばれるようになります。
しかし、そんな坂本氏でも家業の製薬会社の経営の立て直しは大失敗に終わり、世間からの厳しい批判にさらされました。
-

-
いかに学問とビジネスの現実がかけ離れているか、よく分かりますね。
<参考>学校教育に介入したエグゼクティブや企業
こういった日本の大学教育を危惧する企業のエグゼクティブもいて、行動を起こしています。
日本電産・永守重信氏
先に挙げた永守氏は、京都最先端科学大学の理事長に就任するやいなや、私財100億円を投じて自ら大学教育の改革に乗り出しています。同大学では永守氏主導のもと、2022年に経営学研究科経営管理専攻(MBA)も設置される予定です。
三菱商事・元代表取締役副社長の宮内孝久氏
神田外語大学の学長に就任。
ライフネット生命創業者・出口治明氏
立命館アジア太平洋大学の学長に就任。
大学や高校を開校した企業
トヨタ自動車、KADOKAWA、ソニー、島津製作所、マルハニチロなど
-

-
このように少しずつではありますが、民間企業が大学教育に介入することによってビジネス社会で通用するスキルや知識を身につけさせる風潮は広がりつつあるのです。
【就活と大学の専攻は関係ない理由③】学生生活に問題のある学生が多い
「大学生の学習・生活実態調査」※では大学の授業を選ぶ際に60%以上の学生が「あまり興味がなくても単位を簡単に取れる授業が良い」と考えている実態を明らかにしています。
※2016年「第3回大学生の学習・生活実態調査」ベネッセ教育総合研究所より
■1週間で過ごす時間について※
|
「大学の授業」「授業の予習・復習・課題をおこなう」 |
14.4時間 |
|
「友達と遊ぶ」「サークル活動」「アルバイト」 |
15.2時間 |
|
「インターネットやSNS」「テレビやDVDなどの視聴」 |
14.1時間 |
※2016年「第3回大学生の学習・生活実態調査」ベネッセ教育総合研究所より
-
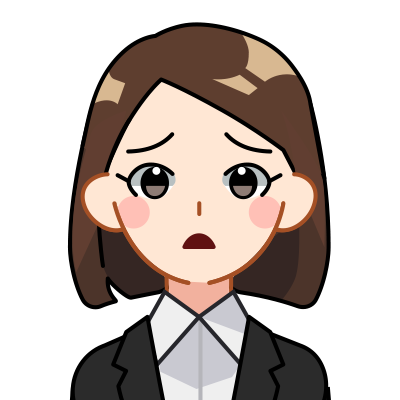
-
(よかったぁ。私だけじゃなかったんだぁ)
わ、私はちゃんと勉強してましたけどねっ!
でも大学生の『普通』がこのデータ通りだと、企業が大学で学んだことを仕事に活かすのを期待しないのも納得です。 -

-
日本の大学は「入るのは難しいが、卒業するのは簡単」と言われています。
多くの学生たちがその状況に甘え、勉強以外のことに情熱を注いでいるのですから、大学で学んだことが仕事で活かせなくて当たり前なのです。
もちろん、真面目に将来のことを考えて、ビジネス社会で使える知識や能力を身につけようと必死に勉強している学生もいると思います。しかしそのような人はごく一部だと断言できます。なぜなら、これまで嫌々テスト勉強をさせられてきた18,19の若者が、将来を見据えた勉強を自主的にできるわけがないからです。
こういった実態は学生本人の問題ではなく、ちゃんとしつけをしない大人の責任です。
学生を導く大人の意識が変わらない限り、いくら大学の教育が変わっても何の変化も期待できません。
-

-
いずれにしても現状では大学で学んだことがビジネス社会で役立つことはありません。その前提に立ったうえで、就職先を選んだほうがよいでしょう。
まとめ
- ほとんどの企業は業務に大学の専攻を活かすことを期待していない。
- 日本の大学の講義はビジネス的な観点ではなく、学問的な観点に基づいておこなわれているのが実情。
- 専門性の高い専攻でも、入社直後からその知識を活かして第一線で活躍することはできない。
- 大学で学んだ内容が仕事で活かせないのは、学生生活にも問題がある
- 「大学で学んだことがビジネス社会で役立つことはない」という前提に立ったうえで、就職先を選んだほうがいい。
書籍版『失敗しない就職活動』では、この他にも就活に役立つ様々なノウハウが書かれています。
学生の皆さんには本文データを無料でプレゼントしておりますので、ぜひこちらからダウンロードください。